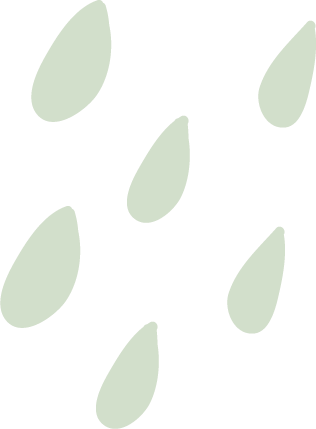国内外の技術を
取り入れた
ナチュラルな農業
natural farming

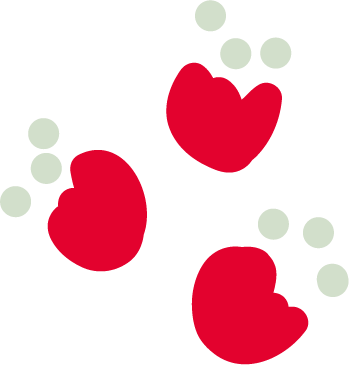
昨年トラクターが壊れ、母親と修理するか買い替えるか悩んだ挙句、抽象度を一段上げて「そもそも耕さなくて良い農法に切り替えたらいいんじゃね?」という結論に至りました。 よく考えてみれば、畑って不自然ですよね。畑の中には木が生えていないし、草は取り除かれ、硬くなった土には外から堆肥を持ち込んで機械で強引に耕して土づくり?それを否定するわけではないですが、割と不自然。 無農薬栽培はもちろん、私は農法ももっと自然に寄せていきたいと考え、ネットで調べていくうちにドイツ発祥の「ヒューゲルカルチャー農法」に辿り着きました。 コンセプトは「森の再現」。畑に木の幹や枝葉を積んでいき、まるで丘のように畝を仕上げていく農法で、この農法だと10年くらい無施肥で野菜を育てられるそう。 「森の再現」なんだったらリン酸カルシウムの補給に鹿の骨も入れてやれ、と私は鹿の骨も入れました(そしたらキツネ?に穴を掘られましたw)
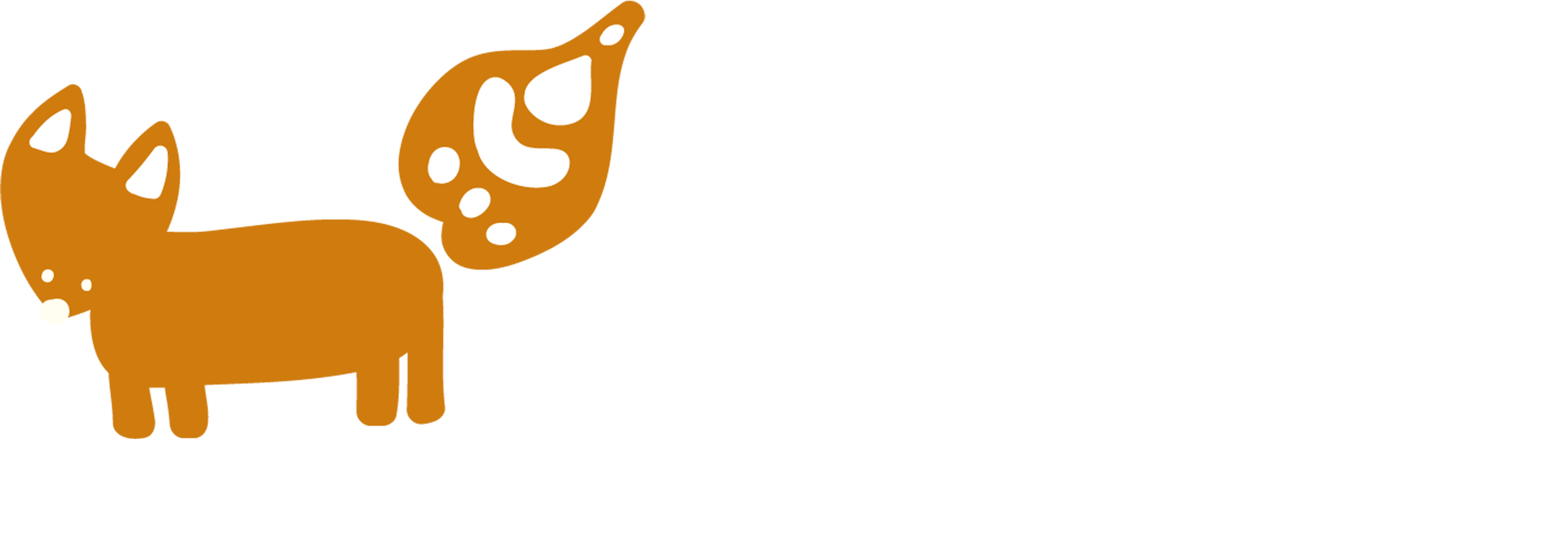


この農法、どのようなメカニズムで野菜が育つのか、その詳細は別途書きますが、要は菌の活用です。 日本ではヒューゲルカルチャーの亜種に当たりそうな「菌ちゃん農法」が流行っていますよね。 基本的なメカニズムは似ていると思います。 無施肥でも、いや、無施肥だからこそ菌が野菜とコラボしてくれて、健やかな野菜が育つようです。 子育てでもそうですが、過保護になると成長を阻害しちゃいますもんね。 与えすぎは良くない。栄養は自分で現地調達。 それは放し飼いの鶏にもお願いしていて、ある程度は与えるけど、それ以上欲しかったらエサは自分で獲ってこい、と。 話が少し逸れましたが、令和7年の2月から、このヒューゲルカルチャーのレイズドベッドを作り始めました。 どんな野菜が収穫できるようになるのか、楽しみです!(これを書いている今は令和7年3月)


また、令和7年の春からは、「農家民宿 村の宿」の庭を活用したアクアポニックスシステムも導入します。 アクアポニックスとは、魚介と野菜を同じシステムで育てる、アメリカ発祥の比較的新しい持続可能な循環型農業です。 水槽で魚などの魚介類を養殖し、フンの混ざった水をポンプアップして野菜を水耕栽培。 水槽にはキレイになった水が戻るので、魚が快適に過ごせます。 これは言わば、大自然の循環を人工的に模したシステムですね。 地域から出る有機物を魚に与えるだけで野菜が採れるなんて夢のようだし、その魚も釣って食べていただけるように企画準備中です。

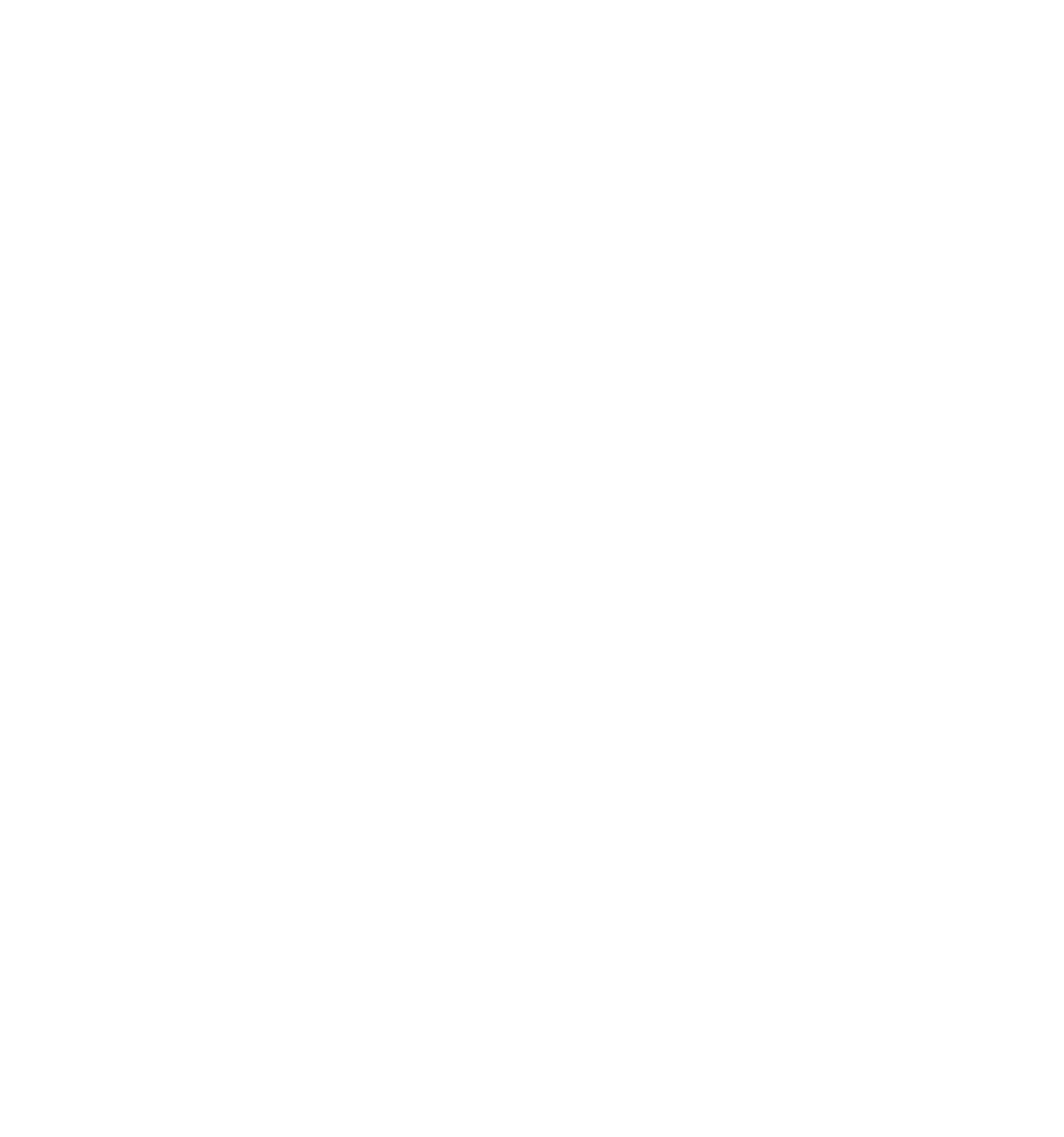
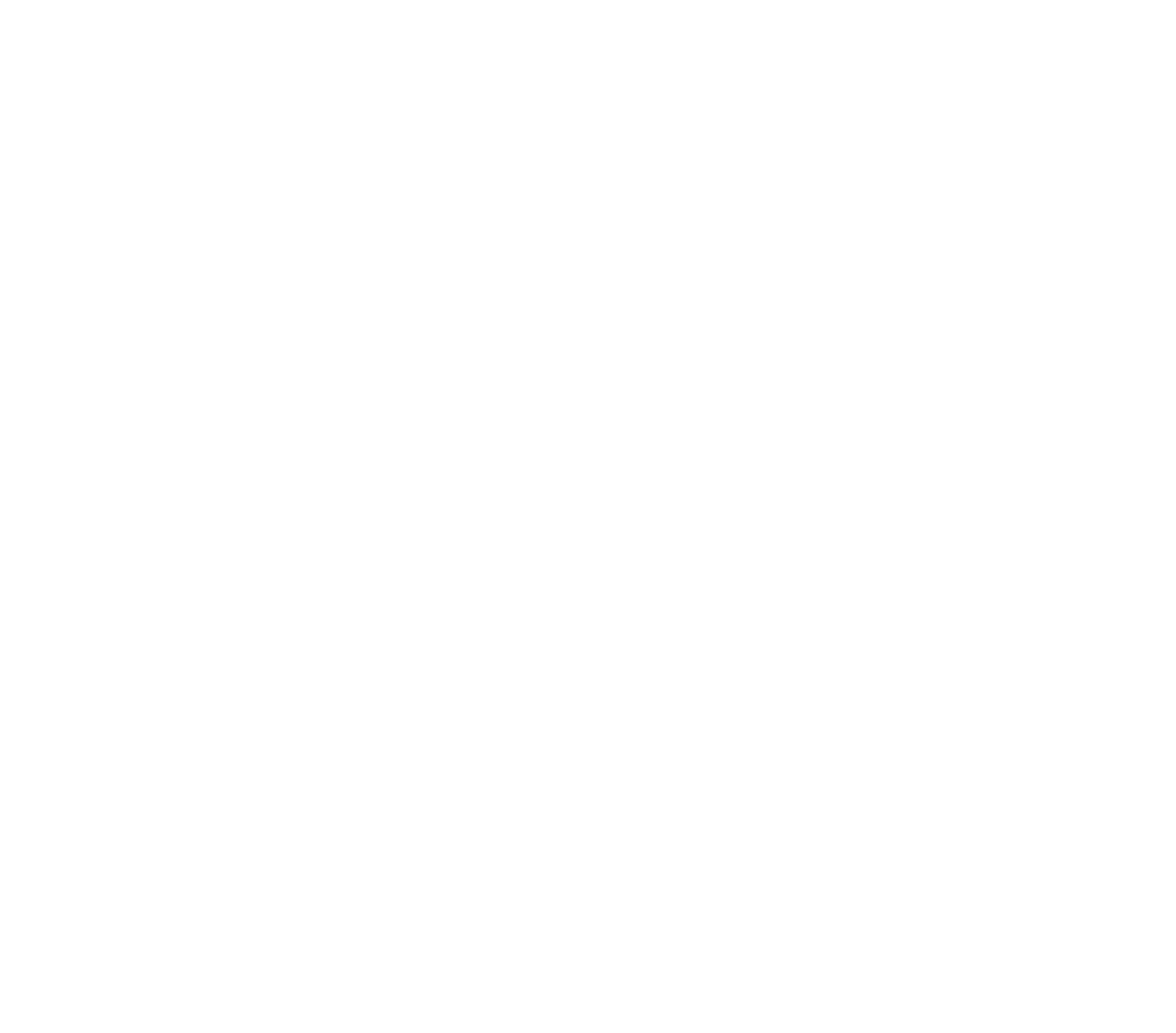


村の自立的な暮らしを
支えてくれる
動植物たちと、
障がいのある方々
independent living



日本の養鶏は卵を安価に供給するため、その9割以上が狭いケージに閉じ込めた「ケージ飼い」となっています。
それが「卵は物価の優等生」と言われる所以ですが、一方で動物福祉の観点では、鶏らしく生きられない飼い方が問題視されており、ケージ飼いはヨーロッパではすでに禁止されています。
また鶏小屋の中で飼う「平飼い」もありますが、人間と一緒で群れに序列を作る鶏たちを閉鎖空間に閉じ込めると、いじめが起こりやすくなり、人間と一緒で群れに序列を作る鶏たちを閉鎖空間に閉じ込めるといじめが起こりやすくなり、突かれて痛めつけられ、死んじゃうこともあります。
 そこでみんなの村では、鶏たちは広々とした屋外で放し飼い。
温かい陽射しの下、広い運動場を走ったり、穴を掘ってひなたぼっこしたりして、鶏らしく自由にストレスの少ない環境で過ごしてもらっています。
鶏を突くことはありますが、逃げ場がたくさんあるし、そもそもストレスが少ないので陰湿化しません。人間の皆さんも、いじめに遭ったら外の世界へ移動しましょう。
一方で屋外には天敵もいっぱい。
これまでキツネや鷲に捕食されることが多々ありました。
この5年近くで50羽くらいは被害に遭いました。
そこでみんなの村では、鶏たちは広々とした屋外で放し飼い。
温かい陽射しの下、広い運動場を走ったり、穴を掘ってひなたぼっこしたりして、鶏らしく自由にストレスの少ない環境で過ごしてもらっています。
鶏を突くことはありますが、逃げ場がたくさんあるし、そもそもストレスが少ないので陰湿化しません。人間の皆さんも、いじめに遭ったら外の世界へ移動しましょう。
一方で屋外には天敵もいっぱい。
これまでキツネや鷲に捕食されることが多々ありました。
この5年近くで50羽くらいは被害に遭いました。


そこで令和7年からは、番犬シンバの登場です。 真っ黒な大型犬を放し飼いしたおかげで、天敵に捕食されることが著しく減りました。 またシンバも広大な「ドッグラン」で走り回って十分な運動ができています。 エサは市販のドライフードは与えず、丹波市で獲れた鹿肉と野菜を混ぜて与えているので、日々健康で楽しそうに暮らしています。 鶏のエサも市販の配合飼料は与えず、豆腐屋さんから出るオカラや飲食店から出る調味前の生ごみなどをいただき、腐敗しやすい物は発酵処理して与えています (そうしてお世話になっている飲食店には、物々交換で卵を差し上げています)。 他にも村には山羊もいまして、こちらも市販のエサは与えず、放し飼いしているエリアの草や笹を食べて、のんびり過ごしています。 そしてこれらの動物の世話(鶏のエサ作りや採卵、山羊の水やりなど)には、障がい者の就労継続支援A型(最低賃金を保証した就労支援制度)を導入しています。 生き物相手だから単純作業の繰り返しといかず、日々変化のある仕事です。 この職場でしっかりトレーニングを受けて、障がいのある方々が自立的に生きられるよう、願っています。

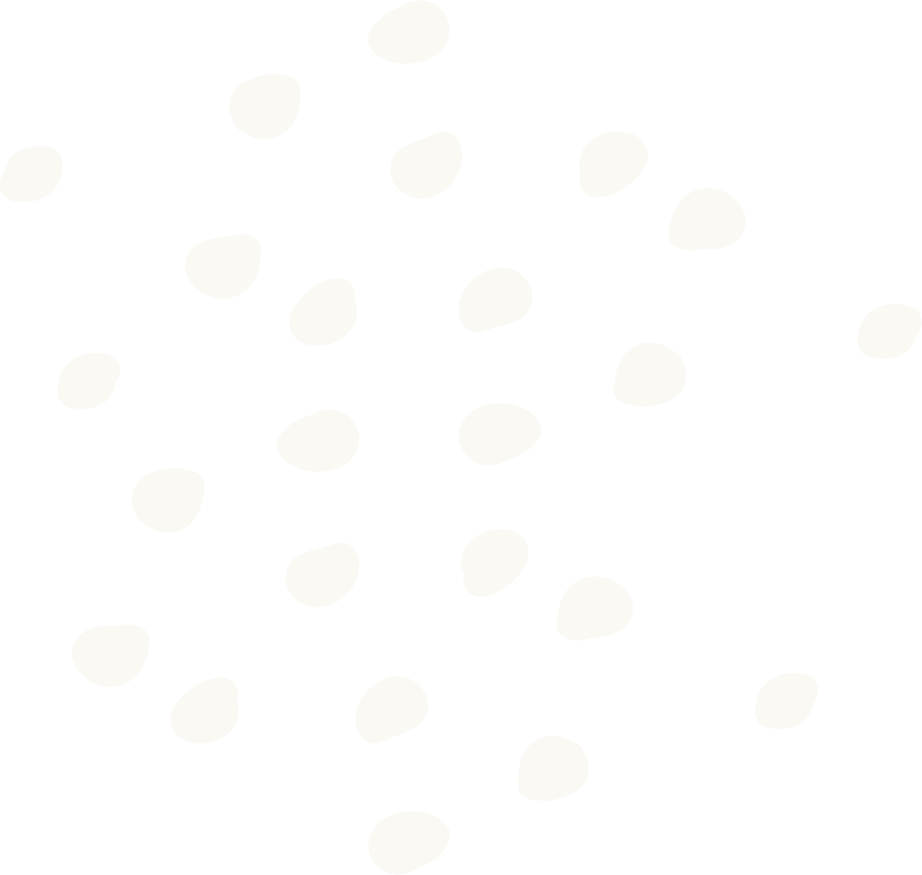
自然エネルギーの
活用
renewable energy

皆さんが故障していなくても車を乗り換えるように、私は故障していないのに自宅の薪ストーブを買い替えてきました。この15年で3台目です。 一口で薪ストーブと言っても、燃費や暖かさが機種によって全く違うので、自分たちのライフスタイルに合ったストーブを手に入れることが重要だと考えています。


一般的には薪ストーブは広葉樹を燃やすことが推奨されていますが、丹波市は杉、檜の人工林が多い地域。 針葉樹の方が手に入りやすく、広葉樹よりも安価です。 そこで色々と調べてたどり着いたのが、スペインはパナデロ社の「イスラ」。 イスラは針葉樹でも広葉樹のようにゆっくり燃やしてくれて高燃費。 そして何より大きな窓からの輻射熱量がハンパない。 とても気に入ったので、3台目となる自宅だけでなく、「農家民宿 村の宿」にも「手打ちそば木琴」にもこのイスラを据えました。 冬に来られたら灼熱の冬を堪能されてください。 ただ、薪ストーブには煙突が必要で、物理的に煙突を通せない部屋は薪ストーブで暖を取れません。 そこで薪ボイラーで沸かしたお湯を各部屋に送り込み、部屋に設置したパネルで熱交換するシステムも組みました。 これによって家の中が全体的に暖かくなります。


一方で夏に薪ボイラーでお湯を沸かすのは辛いので、夏場の給湯は太陽熱給湯。 さらに夏は屋根の上に取り付けたスプリンクラーから、地下水を散水して、打ち水効果で家全体を冷やしていきます。 こうしてできるだけ電気エネルギーを使わなくて済むようにしたうえで、太陽光発電です。 自動車は電気自動車リーフに乗っているので、近い将来はV2H(昼間:太陽光発電→リーフ、夜間:リーフ→自宅)で完全オフグリッドを目指します(お金さえ貯まればすぐやりますw)。 太陽光発電に関しては、農地の上で発電しつつ地上で作物を作るソーラーシェアリングにも取り組んでいましたが、丹波市の農業委員会からまさかの撤去を命じられた失敗談もありますよ! おかげで1000万円ほど損しました。(耕作放棄していたわけではないのに撤去に至ったのは、たぶん全国初!) エネルギーはその地域の環境に合った複数の手段で自給するのが良いと思います。 日進月歩の業界なので、これからも環境への負荷を最小限に抑えつつ、快適な生活を送ることができるエネルギーの自給自足について考えていきます。


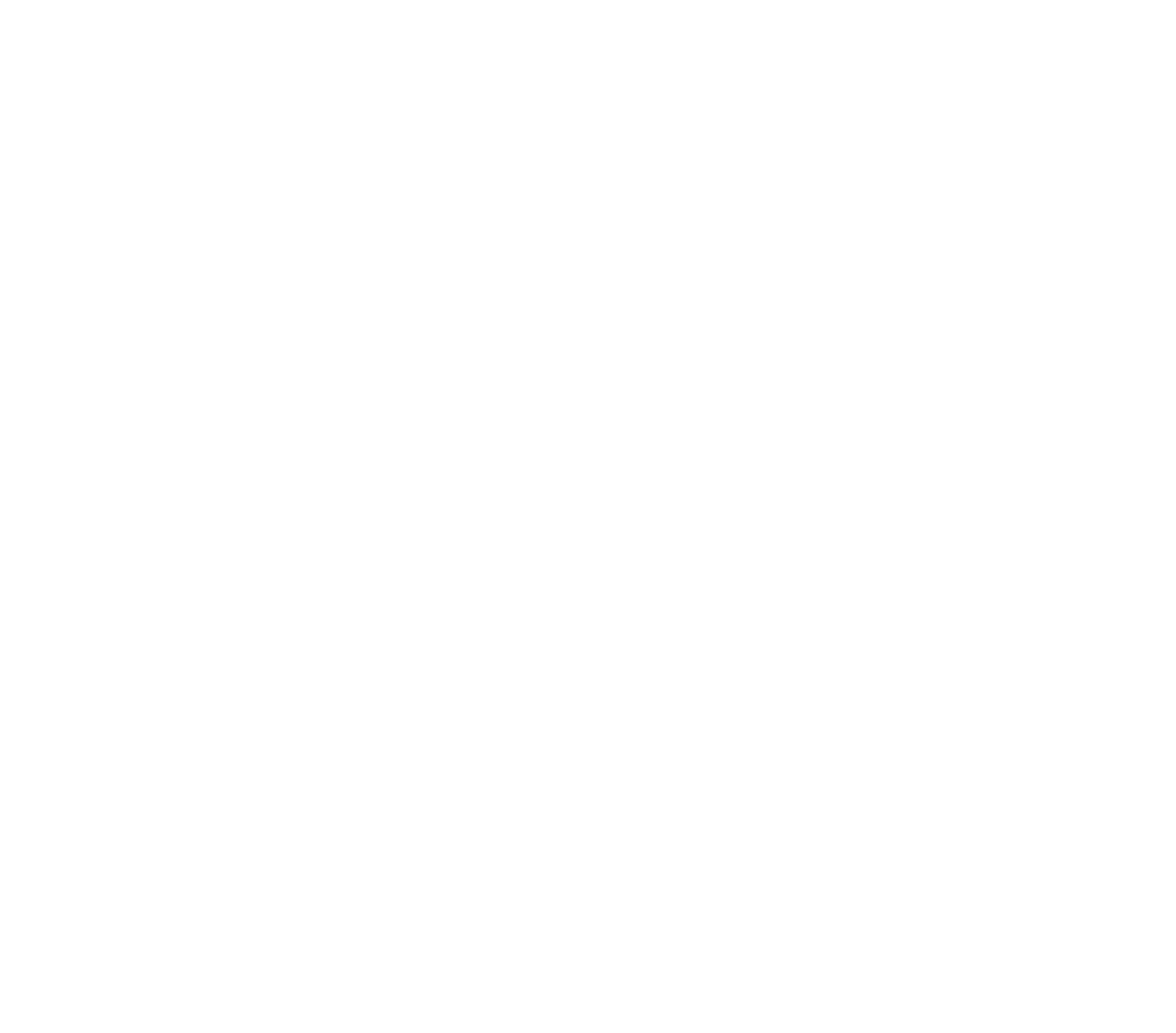


経験を踏まえた学びと
未来への継承
for the future

この村づくりのキッカケが鬱にならない暮らしを作ることだっただけあって、この村には落ち込まずに楽しい人生を送るノウハウがあります。 それは、私が鬱を克服していく過程で見出した「論理的思考力と自己肯定感の両方が高ければ、人は鬱にならない」という考え方がベースにあります。


論理的思考力の中でも「抽象思考」はとても大事。トラクターが壊れてトラクターを直すか新しいのを買うかで悩んだ挙句、不耕起栽培に踏み切ったことは先に触れましたが、行き詰まった時に「そもそも?」と問い、抽象度を上げることで、視界が一気に開け、打開策が生まれてくることが多々あります。 他にも例えば、老後の年金は多くを望めない、一体いくら貯蓄があればいいんだ、という悩みは、そもそもお金のかからない自給自足の暮らしを作っておけば安心です。 このような思考回路を持っていれば、人生をより楽しく送ることができます。 また、自分の良い面もダメな面もひっくるめて、自分は自分でいいと感じられる「自己肯定感」に関しては、主に幼少期の周りの大人との関わり方で身についていきます。 だから、その子が将来的に強くしなやかに生きていくマインドを身につけるのか、鬱や引きこもりになりがちなマインドを身につけるのかは、こどもの頃の関わり方が影響してきます。


小難しく言うと、子どもの人権を守ってやりましょうという話で、この考え方をもっと地域社会に広めたく、私は2020年に市議会議員になって「丹波市こどもの権利に関する条例」の制定までこぎ着けました。 また地元の方々には、これら論理的思考力と自己肯定感の両方の高め方を、親子セットで伝える「親子塾」を開催しています。 親と子、どちらか一方に話をするより、親子セットが絶対効果的です。 なぜそこまでするのかと言うと、やはり自らの経験があるからです。 父親から暴力を受けたり進学先を決めつけられたりして自己肯定感が育まれなかった私はプライドだけ高く、大人になってから事業のトラブルで鬱になって苦しみました。 だからもうこんな人間を生み出さない社会にしたいと考え、この活動はライフワークになっています(ちなみに今では父親と仲良しですよ)。 農家民宿にお泊まりの方も、ご希望があれば「親子塾」を開催することが可能です(11,000円/60分)。

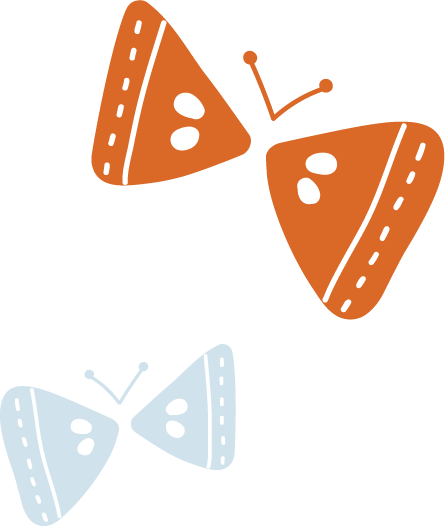
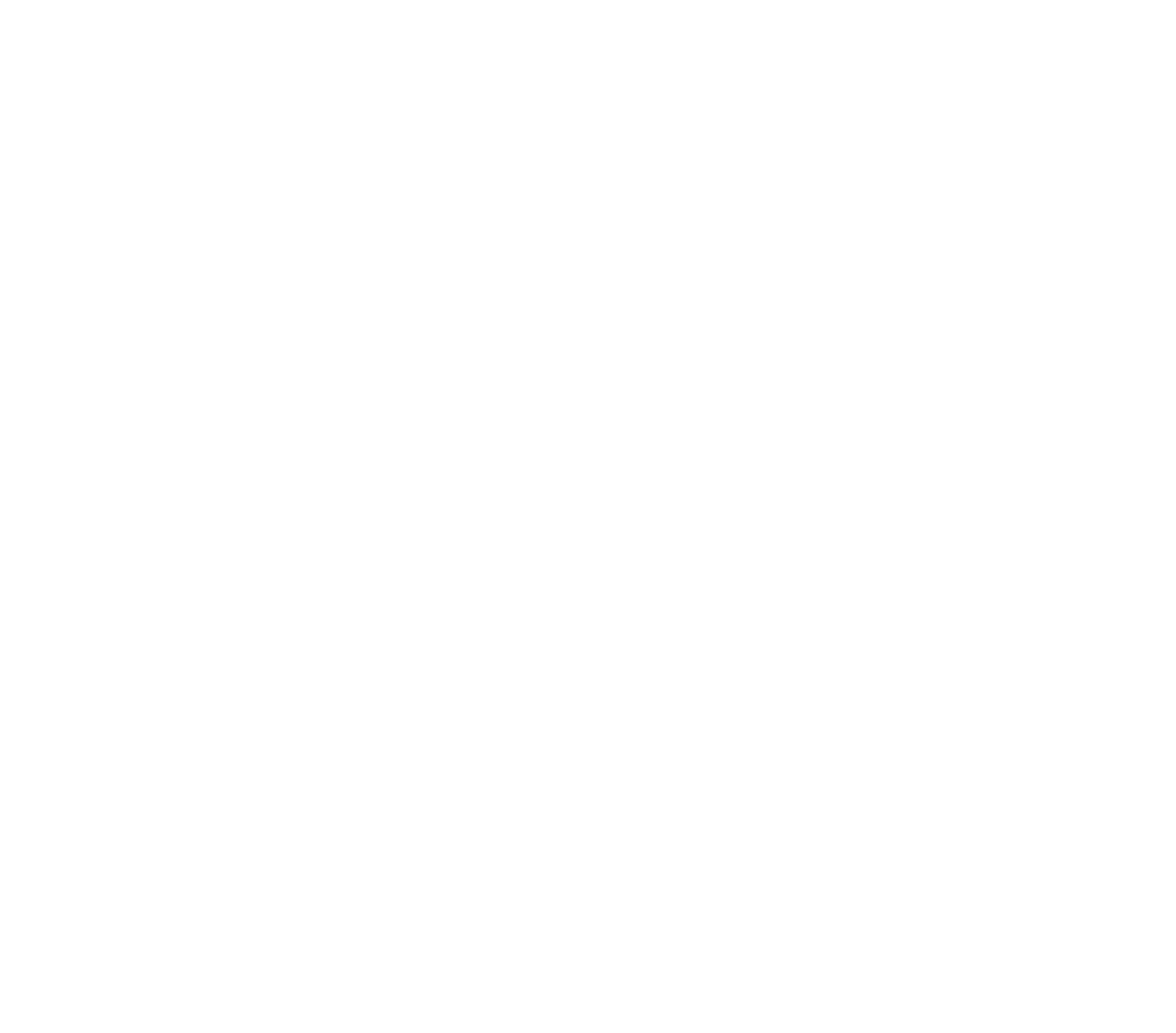


コロナ禍で見えてきた、
これからの豊かさ
The abundance

コロナ禍で物流が止まった頃、都市部で暮らしていた一部の人たちが焦り出し、田舎への移住が急増しました。移住された方々に話を聞くと、田舎の方が安全安心な暮らしができるから移ってきた、とのことでした。


要は、都市部では米や野菜などの食料を十分に生産できないから、物流が止まってしまえばいくらお金があっても食べていけないけど、その点、田舎は食料を作り出すことができるから、「自分たちで作っちゃえば安心だ」と移住してこられたようでした。 先に述べた「抽象思考」をして、食料を生産しづらい都市部で行き詰まりそうになった人たちが、「そもそもなんで都市部に居るんだっけ?」と問い直し、自らが田舎で生産に励むようになられたのでした。 それは食料だけに留まりません。食料に加えて、飼料、肥料、燃料の「四つの料」も都市部では作り出すことが難しい状況です。そんな都市部では資本主義社会の中で熾烈に争い、勝った者が多くを消費し、負けた者が貧しい思いをします。一方で自然豊かな田舎では人間相手に戦わずとも、自然と調和した者が「四つの料」を生み出し、豊かな暮らしができるようになります。 人間同士で戦い、勝った者が消費する都市部の暮らしと、自然との調和に没頭して生産する田舎の暮らしと、どちらを選ぶのかという物の見方がここにあります。


そしてコロナ禍以降、国内外に目を向けると食糧危機の気運が一気に高まった印象です。ウクライナの戦争や円高で、元々食料自給率の低い日本の弱点が露呈されました。 日本は人口減少が続いていますが、世界では人口爆発が続いていて、2050年代には100億人を突破すると言われています。そして日本経済が停滞している間に諸外国は力を付けてきています。私は、日本が諸外国に買い負け、飢える日は近いのではないかと危惧しています。 今の日本は食料だけに留まらず、飼料、肥料、燃料の「四つの料」を輸入に頼ってしまっています。そんな国で暮らす以上、豊かで安全安心な暮らしを実現するためには、今のうちにこの「四つの料」を自給できる自立的な体制を構築しておきたいと私は考えています。 そんな危機感を感じながらも、でも普段の暮らしは家族や仲間たちと楽しく過ごしています。楽しく備えて有事を迎える、そんな感じですかね。 コロナ禍をキッカケに、これからの生き方、在り方が見え隠れしているように感じるのは、私だけでしょうか?